同時刻の相対性をめぐる諸問題
村山 章
- 序
- 一 相対性理論の本質
- 二 四次元時空の実在性と我々の意識について
- 三 因果的決定論と時空的決定論
- 四 量子力学と同時刻の相対性
- 五 倫理学上の問題について
序
私の問題意識 相対性理論の本質は「同時刻の相対性」という点にある。私はそれを前回の論文「相対性理論と同時刻の相対性」において、特殊相対論の基本命題を導く中で示したが、相対性理論を相対性理論たらしめているものがこの点にあることは、一貫して示していけることである。
一般相対論においても、もし単に重力系と加速度系の等価性のみが指摘されて、同時刻が絶対的のままであったなら、ニュートン力学に比してかくも奇妙な結論は導かれなかったと思われる。慣性系に対する重力系や加速度系の相対論的特徴が表れる根拠は、まさに同時性が変化していくところにあるのだ。その変化のあり方が、質量分布の非一様性のため大域的に一様でないところが重力系の加速度系に対する違いである。
ところで、同時刻の相対性は、互いに距離を隔てて速度を異にする他者の存在を考えると、過去と未来について決定・未決定の区別をつけられなくさせてしまう。すなわち、「過去は未来と同じく決定されていない」という、常識とかけ離れた世界観か、「未来は過去と同様、完全に決まっている」という宿命論かのいずれかを採用せざるをえなくなることが実に単純な論理で導かれてしまうのである。それが前回の論文の最後に示した論証であった。
この論理とその帰結に気付いたのは、私が二十三歳くらいのときだったかと思う。当時、哲学的関心から時間・空間の問題と取り組む中で、相対性理論をどう理解したものかと考えていた時だった。卒論のテーマはこのとき決まった。だが、私にはまるで自信がなかった。第一に、私は物理学が専門ではない。どこかに誤解があってのことではないかと思った。さらに、結論が気に入らなかった。およそ、ニヒリズムかペシミズムにしか結びつきそうもないように思える帰結を胸を張って主張する気にはなれない。卒論は歯切れの悪いものになった。その後、十年以上の歳月が過ぎた。私は物理学とはまるで縁のない世界を歩んでいた。しかし、心の隅でこの論理がいつも気になっていた。どう考えても、この論理の誤りが見出せない。少なくとも、相対論の内部においては。それで、量子力学と対決させねばならないと思った。だが、量子力学は簡単ではない。それでも、量子力学が同時刻の相対性を否定する方向に展開されているわけではないことくらいは浅学の私にもすぐに判ることであった。問題は物理学の内部のみで解決しきれるものではないだろう。私はそう直観した。
「過去は未決定である」という前提か、「未来は完全に決定されている」という前提に立って、我々の世界観そのものを根本的に組み直すべきではないか、そんな大胆な気持がよぎるようになった。前者の前提に立つと、何故、過去は決定されていると我々の意識には判断されるのかという問題を解決せねばならない。これは途方もなく難しいように思えた。むしろ、後者の前提に立った上で、我々がいかにペシミズムに陥らないで生きて行けるか、その気構えを探求した方が簡単そうだと思った。私の問題意識の根底はこんなところにある。
考察課題のまとめ 私はこの問題を次に掲げるようなテーマに分解して取組むことにした。
(1) 相対性理論の本質が「同時刻の相対性」にあることを示すこと。
(2) 四次元時空の実在性の証明と我々の意識における運動する三次元性の証明
(3) 因果的決定論と時空的決定論について
必然性に対する我々のパラダイムについての検討
(4) 「同時刻の相対性」を量子力学の中でどう捉えるか
観測問題と非局所的連関について
(5) 倫理学上の問題について
自己意識についての考察
本稿では、上記各テーマの概要をかいつまんで述べることにする。掘り下げた議論は独立した別稿で今後扱っていきたい。前回に出した「同時刻の相対性と物理学的必然性について」という一本の論文を連載していくという形式は、本誌の性格上無理があるためとりやめさせていただくことにした。
一 相対性理論の本質
私が大学に在学していた当時、よく議論のテーマになったのが「自由と必然」についての問題であった。また、弁証法とは何かいうことについても大きな関心があった。理論的探求の一つの切り口として私はヘーゲルが(そしてエンゲルスらが)弁証法的矛盾の例として位置の移動に関するゼノンのパラドックスを取り上げて説明しているところに注目した。私には論理上の概念である「矛盾」が客観的事物の運動の原因のように言う考え方がなかなか納得できなかった。
一方で私は、時間・空間とは何かというテーマに関心を持っていた。その方面からは当然、現代物理学ではこれに対してどのような了解がなされているのかを知る必要が生じる。さしあたって、相対性理論を理解しようと思った。そこでは「四次元時空」という考え方が生じてくる。このとき私は、もし、物体の運動を四次元時空内の世界線(質点の各時点を結んだ時空内に延びた線)として捉えたならば、ゼノンのパラドックスは消えるのではないかと思った。運動する物体は、ある位置にあると同時にない、その矛盾故にゼノンは運動そのものを否定し、ヘーゲルは逆に運動の本質は矛盾そのものであると説いた。だが、四次元で考えたら、運動する物体の存在とは、世界線がただそこにあるというだけのことで、どこにも矛盾はないのである。
しかし、我々にはイメージすらできない四次元とは何なのか、それは実在のものなのか、何故、相対性理論は四次元なるものを考えなくてはならなかったかという問題が沸上がった。
哲学者が相対性理論の本質を探ろうとするとき、多くの場合、アインシュタインの思想的系譜を辿ろうとする。するとマッハやポアンカレの影響等が取り沙汰されて、認識主観の相対性がクローズアップされたりする。しかし、私は、こういった多くの解釈はどうも言葉の言換えにすぎないように思えて釈然とした気持になれなかった。認識主観の相対性では、相対性理論はまるで理解できないのだ。一方、また多くの物理学者の解説もそもそも相対性理論とは何なのかという点で釈然としたものが得られない。例えば、長沼伸一郎氏の労作「一般相対性理論の直感的方法」では、次のように述べられている。
「なぜ」実際に時計が遅れたりするのか、という問いを今、発されても少々困る。だいたい相対性理論そのものがその問いには答えていない。相対論が説明するのはあくまでも「どのように」遅れるかというところまでである。実際、相対論の成立の経緯について言えば、ただ単に、そうでなければ矛盾が出るからということで作られた理論と、半信半疑で行われたたくさんの実験結果がほぼ完全にお互いを支持しているのだと、そういうふうにしか現代の物理学者といえども答えることはしていないのである。(同書二十九ページ)
しかし、私はこのように諭されてもなお納得できないのだ。
それでも、はっきり自覚できたことはある。相対性理論は時空図を描くと実にわかりやすいということだ。しかし、「時空」とは何なのか、何故、時間と空間を一つにしなくてはならないのかということが問題だ。私は暫く考えていくうちに、これを不可欠にさせているものは「同時刻の相対性」にほかならないという考えに至った。
「同時刻の相対性」は光速不変の原理からただちに導けるもので、およそ、どんな解説書にも必ず出てくる基本的な事柄である。しかし、これはたいてい、いくつかの奇妙な結論の一つくらいに位置付けられていて、これを理論の本質としてはっきりと明示した形で展開している解説書は少なくとも私は知らない。だから、その作業が必要だと思った。
さしあたって、私は同時刻の相対性から、時計の遅れ、物差しの収縮、そしてローレンツ変換を導くやりかたを考えた。それが前回の論文の内容になる。
さらに、質量とエネルギー・運動量の問題、相対論的力学の内容展開が必要になる。これには、四次元ベクトルの考え方を導入せねばならない。世界線の単位接線ベクトル(四元速度)に静止質量を掛けたもの、それが四次元的な意味での運動量を表わす。エネルギーとは、本質的にはそのベクトルの時間成分(の増分)のことであり、従来の運動量とは、その空間成分のことであったことが示される。(有名なE=mc2はこのへんから導ける。)
ここで何と言っても重要な概念は「四次元」という考え方なのである。四次元時空とは何なのか、それは実在のものなのかといった点をはっきりさせないままで、理論だけ展開していっても、いつまでも釈然としない気持が残るであろう。この四次元について考えるための最大のキーは、「同時刻の相対性」なのである。その点にについては次節で述べる。
相対論の展開の次のステップは加速度系についてである。加速度系というのを、次々と異なる慣性系に移っていく系だとみなすと、異なる慣性系は互いに同時性が異なるわけであるから、加速度系は同時性が次第に変化していく系である。この点が重要である。これ故に、加速する方向に距離を隔てて存在する慣性系の時間は、加速度系に比して急激な進み方をすることになり、例の双子のパラドックスが成立する。このことはたいていの解説書で指摘されていることであるが、私はむしろ、加速する方向と反対方向にかなりの(世界線の「曲率」半径を越える)距離に位置する慣性系での時間進行に注目したい。この系は加速度系を基準に考えれば時間進行が逆転していることになるのだ。こういったことは四次元時空の存在を前提にしないと理解するのが困難である。
そして、一般相対性理論へと進む。ここでの基本コンセプトは、自由落下系は局所的には慣性系と変らないということである。落下しているものは慣性運動しているだけであり、加速的に迫って来るのはむしろ地表という巨大な壁の方なのである。あるいは、重力系は、局所的には加速度系と変らないとも表現できる。地表に静止している系は上空方向に地表から押されて加速されている系だと考えてもよいのだ。かくして、「重力」という名の慣性力が発生するのだと。だが、このような等価性は局所的にのみ言えることであり、大域的には加速方向等が違ってしまう点が重力系の特徴である。すなわち、重力系の本質は時空の歪みにあるのだということになる。この歪みは四次元的なものであり、同時性はますます複雑に相対化されていく。そして一般的な数学的表現には、四次元のテンソル解析という非常に高度な手法が要求されてくるのである。
indexへ
二 四次元時空の実在性と我々の意識について
相対性理論にとって、四次元時空は理論展開上実に根本的な表現形式である。しかし、直接的にはこれはあくまでも表現形式でしかない。四次元時空とは実在するものなのか、単なる便宜上の論理形式にすぎないものなのかは、表現上、論理展開上の有用性からのみでは判断できない。だが、この点をはっきりさせないままでおくことが相対論をわかりにくくさせている一大要因ではないだろうか。
四次元時空は、H・ミンコフスキーの提唱したもので、三次元ユークリッド空間の単純な形式的拡張ではなく、ローレンツ変換に対応して、時間方向に特異な計量構造をもっている。これは、一般相対論でも線形的基礎をなしている。
ところで、四次元時空の実在性を立証するということは、現在の空間のみならず、過去や未来の空間も実在しているということを立証することである。ここで、「同時刻の相対性」に着目しよう。今の私と距離を隔てて私に向ってくる者にとっての現在の空間は私の未来を含んでおり、私から離れて行く者にとっての現在の空間は私の過去を含んでいる。ここで、今の私が実在し、かつ、実在するものにとって同時にあるものは実在するという命題を真とすれば、過去から未来にわたってすべての時空点(事象)は実在することになる。ここで前提となった命題を否定することは私にはたいへん困難に思える。従って、過去から未来にわたるすべての時空点は(今の私にとっての)現在の時空点と同等の実在性を持つと考えざるをえない。すなわち、四次元時空は実在する!
こんな単純な論理で証明しきってしまっていいものなのか、私は暫く否定的な姿勢で、この論理の誤りを探ろうと思った。その一つが光円錐に着目した考え方である。先程は、同時に存在するものは実在するということを前提に考えたが、我々は同時に存在しているものを同時に認識することはできない。いかなる情報も光速は越えられないからだ。もし、実在するのは過去の光円錐「面」上の事象であるとすれば、同時刻の相対性にもとづく論理は成立しなくなる。光円錐「面」は、速度の違う別の座標系に移っても不変だからだ。だが、この発想はただちに破綻することがわかる。何故なら、一つの時空点「今の私」を基準にしてこそ光円錐は唯一絶対的だが、距離を隔てた他者の存在を考えたら、光円錐は無数にある。「今の私」こそが唯一の宇宙の中心であるというような世界観でも持たない限り、この考え方は不可能だ。やはり、四次元は実在する。この確信はさらに強まった。
しかし、問題はこれからである。四次元時空においては、「運動」という表象は消滅する。あるのは絶対静止の四次元立体である。あるのは運動する質点ではなく、静止した世界線である。ある世界線の速度とは、基準になる世界線(時間軸)に対する傾きを意味する。どこにも「運動」という表象が顔を出すことはない。にもかかわらず、厳然たる事実として、我々の意識においては、世界は運動する三次元の流れなのだ。我々にとって、時間とは相対性理論が扱うような空間化されたものではなく、「意識の流れ」のバックボーンとして存在するある種の計量として捉えられている。この意識の事実はどう説明されるものなのか?私はこの問題についてずいぶん考えてきたが、完璧な解答と確信できるものはまだ得られていない。しかし、意識といえども四次元時空の外に存在しているわけではない。意識もすべての諸事物と同様、四次元時空内存在である。このことを踏まえた上で、私はこの問題を以下のような問いに分解して、段階的にアプローチしてみることにした。
(a) 何故我々の意識においては、同時刻は絶対的であるのか?
(b) 何故我々の意識においては、時間方向の広がり(延長)の観念を持ちえないのか?
(c) 何故我々の意識においては、世界の四次元的な幾何学的性質を体験できないのか?
(d) 何故我々の意識においては、時間の方向性が一方的なものなのか?
(e) 何故我々の意識においては、「世界」の三次元的「断面」の連続的継起という形態が生じるのか?
(f) そして、「今」とは何か?
(a)については、私は、我々の心身のスケールという点に着目して考える。我々の心は、我々の身体の数億倍もの距離を光が進んでしまう時間を一瞬の時間としてしか感じることができない。それほど我々の意識過程はゆっくりとしたものなのだ。従って相対論的には自然な、光速が1となるような時間・空間の単位系とはかなり掛け離れた秒とメートルという単位系で日常を過ごすことになる。これでは相対論的効果は体験できない。このような心身のスケールを持つものにとっては、同時刻は殆ど絶対的なのである。
(b)、(c)については、四次元時空のミンコフスキー的構造の特徴から、答えていこうと思う。
(d)については、宇宙論的考察が必要になってくるだろう。 (e)、(f)に至っては、問いに答えることそのものに対する考察というようなメタフィジカルな姿勢まで必要になってくるのではないかとも思っている。はっきり言って、難しい。
これらについては、また、稿をあらためて論述していきたい。
indexへ
三 因果的決定論と時空的決定論
「同時刻の相対性」は四次元時空の実在性を証明する。すなわち、過去も未来も常に存在しているということである。それならば、その存在している未来は未決定なのか、決定されているのかということが当然気掛りになる。
この問題に関しても、「同時刻の相対性」は明確な証明を提供する。それが前回の論文の最後に述べたことである。すなわち、同時刻が相対的ある限り、過去と未来は決定・未決定ということに関して同一の属性を持たなくてはならない。もし、過去は完全に決定されているという前提(常識的にはこれは否定し難い)に立てば、未来も完全に決定されている。それは、距離を隔てて私に向ってくる他者の存在が証明する。彼にとっての現在は私の未来だからだ。もし私の未来は未決定だと言えば、私にとっての今の彼の過去の一部もまた未決定だと言わねばならない。(図1)
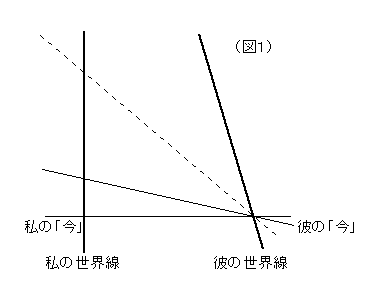 もし、決定されているのは、過去の光円錐「面」よりも過去の事象であるという観点に立てば、「同時刻の相対性」の論理からは解放されるが、今の私が唯一絶対の宇宙の中心であると考えなくてはならなくなる。
もし、決定されているのは、過去の光円錐「面」よりも過去の事象であるという観点に立てば、「同時刻の相対性」の論理からは解放されるが、今の私が唯一絶対の宇宙の中心であると考えなくてはならなくなる。
結局、相対性理論が許容する決定性に関する世界観は次の三つのうちのいずれかでしかない。
(1)過去も未来も完全に決まっている。
(2)過去も未来もともに決まっていない。
(3)あるのは今の私のこの意識のみであり(独我論)、過去は決まり、未来は決まっていない。
独我論を排除する形で、過去は決まり、未来は決まっていないという立場を貫くためには、同時刻は絶対的であることが要請される。相対性理論は間違っていて、ニュートン物理学へ戻るべきだという立場に立つ必要がある。この立場については、いずれ別途検討することにして、相対性理論は間違っていないという前提で議論を進めよう。
(3)の立場(独我論)を純然たる形で主張する人は少ない。もっとも、この立場は主張すること自体の意味が問われてしまうので、主張しないだけでこの立場に立っている人は意外に多いのかもしれない。しかし、この立場を純然たる形で貫くのはかなり強い意志が必要であろう。ここでは物理学は私の意識の「客観的法則性」についての科学である。
(2)の立場では、「何故、我々の意識において、過去は一意的に決まっているように現象するのか」という問題が重くのしかかってくるだろう。過去の事象に対して、私の認識は多くの他者と一致してしまうのは何故なのか?私の知る他者とは私にとっての他者にすぎないので、他にも数多くの私の知らない同じ他者がいて、その他者にとっては、私の知らない別の私がいたりするのだろうか?あらゆる場合の数だけ無数の宇宙が並行して存在する。この考え方は、量子力学の観測問題をめぐっての一つの立場、エヴェレットの「多重世界論」に通じるような気がする。この立場はそのグロテスクさにもかかわらず、量子力学上の難問を整合的に解決する(するかのように思える)ので、にわかに支持者が増えつつあるようだ。しかし、量子力学上の問題が解けたとしても、他ならぬ私の知るこの宇宙が何故かくなる宇宙であったのか、あろうとしているのかという問題は、形而上学(メタフィジクス)の問題としてかもしれないが、ずっしりと残るような気がする。多重世界論にとって、「他者」とは、たまたま他ならぬこの私にとっての他者でしかないわけで、私としては多重世界論は「マルチ独我論」と呼べるようなものではないかという感想を持っているが誤解であろうか。いずれにせよ、これは現代の量子力学をめぐる有力な立場の一つである。
ところで、量子力学解釈との関連で言えば、(3)の立場(独我論)は、主流をなしているコペンハーゲン学派の中での最もラディカルな立場に対応しているとも言えるかもしれない。すなわち、(私の)意識が(観測が)世界を作り出す!だが、このような過激な解釈はこの学派の中では主流ではないだろう。大多数の物理学者はおよそ控え目に「わからないことは、わからないでおく」立場であり、「実用上の成果が得られれば、とりあえずそれでいいではないか」という立場であって、形而上学に無用に首を突っ込んで心の平安を乱すようなことはしない。そして、このような立場を論理的に誤りであるとして批判することも難しい。だが、私としてはどうしてもこのような賢明な立場に満足できない。
それはさておき、(2)の立場も(3)の立場も、量子力学とはなんとか両立できそうな気配はあるが、(1)の立場は量子力学とは真っ向から対立しそうである。何しろ、量子力学は決定論的世界像を崩壊させたと言われているのに、(1)の立場はとてつもない決定論だからだ。
だが、量子力学のことは念頭に置かないで、素直に相対論的時空像を捉えた場合、(1)の立場が最も受入れやすい。と言うより、(1)の立場でないと、相対性理論の力学的内容の展開は非常にまどろっこしいものになってしまう。だから、この先、とんでもないどんでん返しを食らうかもしれないという覚悟はした上で、(1)の立場で考察を進めよう。
さて、(1)の立場に立つとして、現実に我々の意識にとって、未来は決まっていないように思えたりするのは何故かという問題は生じる。だが、これは現実の四次元時空においては、情報の伝達は過去から未来への一方向性しかなく、未来のありようを知ることは、一般の我々の意識には不可能になっているからだということで説明はつく。ここでは、「時間の方向性」の問題が絡んでくる。この問題についてはまた別途論じなくてはならないだろう。とにかく、情報は光速以下の速度で、過去から未来への方向でしか伝わらない。言換えれば、未来の光円錐の内側にしか伝わらない。従って、未来の事象からは、(自分の座標系では過去や現在であっても別の座標系に移れば未来でありうるような事象も含めて、)絶対に情報が伝わらないような構造を現実の四次元時空は持っている。少なくとも現代の原則的な物理学においてはこれに反する事例は見出されていない。(量子力学では、非局所的連関という形で、光速より速い速度が論じられたりするが、この場合も情報伝達としての光速突破が成立しているわけではない。ここで、「情報の伝達」とは何かという問題を立てるとおさまりがつかなくなってしまいそうだ。ここでの意味としては、あるものの状態がAかBかというような判定を可能にするような何がしかの物理的状態の伝達とでも表現しておこう。)従って、我々は未来を直接知ることはできず、過去からの情報と、経験の積み上げによって獲得してきた法則的知識とによって予測するというやり方でしか未来を知ることはできない。しかもその予測が完全に正しいという保証はないのである。
ところで「同時刻の相対性」から導かれる決定論というのは、予測可能性という点については実にそっけない。この決定論は、各時空点について、決定か未決定かという属性値の違いとして過去と未来を区別できない、それで過去は決まっていると考えたいから未来も決まっているという結論に導く、そういうものである。未来はただ決まっているというだけであって、どの様に決まっているのかについては全く言及されえないのである。ここが従来の決定論と大きく違っている。
従来の決定論、その典型はニュートンの後継者たちが思い描いた世界観、すべてはニュートンの力学法則に従うわけだから、世界の全物質のある時点での質量や運動状態が初期値として完全に把握できたなら、未来はすべて完全に予測できるに違いないという世界観である。もっとも実践的には、三つの天体が相互に引力を及ぼし合う力学系についての完全な予測をするという課題すらも解くことはできなかった(今でもできない)わけだが、それは人類の技術的未熟さゆえのことと解された。原理的にはニュートンの法則に従ってすべてが決定されているはずだからだ、という信念はゆるがなかった。ここでは、決定性と予測可能性とは不可分である。そして世界の決定性は何がしかの因果的連関によって語られる。
このような古典的決定論を「因果的決定論」と呼ぶことにする。これに対して同時刻の相対性から導く決定論を「時空的決定論」と呼ぶことにしよう。「時空的決定論」は相対性理論(の私が示したような解釈)によってはじめて出現した考え方であって、およそこれまでの決定論というのは実質的な意味で因果的決定論である。さもなくば、物質的因果連関を超越した神の意志に帰着させる神学的決定論であろう。しかし、ここでアウグスティヌスなどを繙いて、神様の問題にまで話を広げるのはやめよう。また、「因果」という概念は東洋人にとってはもともと仏教から受け取ったもので、仏教的世界観との絡みも気掛かりである。しかし、収拾がつかなくなるので、とりあえずここでは自然科学で問題になる決定論に話を限定させよう。もちろん、扱っているテーマが宗教上の問題意識と無関係でいられるものだとは思っていないのだが、問題のレヴェルが違い過ぎるからいっしょくたに論じるわけにはいかないだろう。はたして「時空的決定論」は宗教と真っ向から対立するものなのか、それとも大和解をして宗教的世界観と一体となるものなのか、無視され捨置かれるだけのものなのか、はてさて「時空的決定論」の運命やいかに。ちなみに「時空的決定論」によれば、この運命は決まっているはずである。しかし、今の私にそれを知ることはできない。
自然科学上の因果的決定論について言うと、決定性をニュートン力学にすべて機械的に還元させてしまうような考え方に無理があることは、早晩気付かれることであった。因果的必然性は自然の複雑な階層構造に合せて具体的に解明していかなくてはならない。自然の法則性は、様々な階層に応じて下位の法則性を土台にしつつもそこに還元できない独自の構造を出現させていく。それを地道に研究し、理論を組み立てて、自然の予測をする。それは定性的であったり、蓋然的であったり、条件的であったりするわけで、完璧な形で得られることはむしろまれである。それでも実践的には充分であったりするので、生産や生活に巧みに活用され、人類の歴史形成の一役を担ってきた。
因果的決定論はこういう人類の長い営みを通じて形成されたもので、常に現在進行形の状態にあって、その決定性については必ずしも確定的ではない。その上、さらに高次元な分野にいけば人間の自由意志が絡んでくるので、なおさら不確定さを感じさせる。それで、この決定論は世界観の持主の好みに応じて「かため」だったり、「やわらかめ」だったりする。
ともあれ、近年の科学理論の進展は、とことんかたい因果的決定論を不可能にしてしまったようだ。第一に量子力学によって、さらにカオス理論によって。量子力学は、我々の認識事実との接点においては、本質的に蓋然的(確率的)結論しか導けない理論体系であり、カオス理論は、従来の科学的常識では無視されてしかるべき非本質的偶然的差異が平衡状態に消えることなく、大域的に重大な差異をもたらしてしまいうる自然界の姿を暴き出した。今日、我々は近代自然科学が確立してきた、法則によって成立する自然というパラダイムそのものの意味をかなり深いとこらから問わなくならない状況に立たされているのではないかという気がする。
そんな状況下において、実は一方で全く別の形の決定論----時空的決定論が出現していたのである。しかも、この決定論は「かため」も「やわらかめ」もない絶対的なものである。もし、少しやわらかめに、未来の時空点に「おおよそ決まっている」という属性値を与えたとしよう。すると同時刻の相対性から過去もまた「おおよそ決まっている」にすぎないものになってしまう。だが、我々の意識にとって過去は完全に決まっているわけで結局、(2)の立場の場合と同様の問題を抱えることになる。
量子力学は決定論を崩壊させたというが、それはさしあたり、因果的決定論のことである。それでは、時空的決定論と量子力学とでは折り合いはつくのだろうか。これが、量子論をめぐっての私の主要なテーマである。
indexへ
「波束の収縮が同時に伝わる。」同時刻の相対性にこだわっていた私には、この同時とはどの座標系にとっての同時なのだろうかという疑問が生じた。そこで、私は次のような思考実験を考えてみた。(図2)
四 量子力学と同時刻の相対性
量子論において、ずばり、私が着目したいのはEPR問題である。アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンの三名が連名で量子力学の権威、コペンハーゲン学派につきつけたパラドックス。彼等はこれによって量子力学の不完全さを主張しようとした。その一つに非局所的連関をめぐる問題がある。 二つの粒子A、Bがあるとしよう。それらのある属性はaかb、二種類の値しか取らないとする。(例えばスピンの向きとか光子の偏極属性のようなもの。)そして、二つの粒子は一方がaなら他方は必ずbであり、一方がbなら他方はaであるという力学系を形成しているとする。これは現実にありえる仮定である。これらの粒子がaであるかbであるかは二分の一の確率で決まるとする。量子力学によれば、観測しない限りはこれらは二つの状態の重ね合わせの状態として存在している。
だが、一方の粒子Aを観測すれば、波動関数の崩壊が起こり、aかbかが決定する。それと同時に、他方の粒子Bも観測はしなくてもbかaかが決定するのである。これはAとBとが何億光年離れていようとも成立する。するとAの波束の収縮の情報は超光速でBに伝わったことになる。しかし、光速を越えて何かが伝わるということは許されないのだ。非局所的連関(遠隔作用)はありえない。これは長い間の物理学者の確固たる信念であった。これに矛盾してしまうような量子力学はどこか不完全であるに違いない。これは「神はサイコロを振らない」と言って量子力学の確率解釈に抵抗し続けてきたアインシュタインの晩年の最後の抵抗であった。
しかし、結果はその信念そのものを覆す形で量子力学に勝利が与えられた。ベルは局所性を仮定してある不等式を導いた。これが実験事実に反すれば局所性仮定が間違っていたことになる。まもなく、クラウザーやアスペによってこの不等式は実験事実に合わないことが示された。我々は非局所的連関を認めざるをえないところに追込まれたのである。
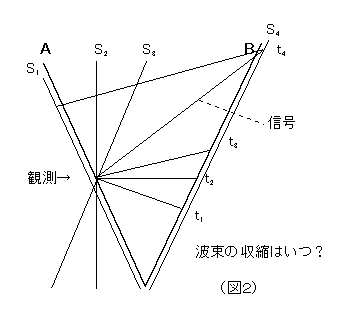 先程の相関的ニ粒子系A、Bを考える。そして、互いに速度を異にする観測者S1、S2、S3、がいるとして、三人と粒子Aはある時刻にある一箇所で出会うとする。その時点で、彼等はAの測定をして属性値aを得たといたとしよう。この時、波動関数の崩壊が起こったことになる。ところで、崩壊したのはAだけでなくBの波動関数も崩壊して属性値bが確定したはずだ。だが粒子Bのどの時刻で崩壊は起こったのだろうか。
先程の相関的ニ粒子系A、Bを考える。そして、互いに速度を異にする観測者S1、S2、S3、がいるとして、三人と粒子Aはある時刻にある一箇所で出会うとする。その時点で、彼等はAの測定をして属性値aを得たといたとしよう。この時、波動関数の崩壊が起こったことになる。ところで、崩壊したのはAだけでなくBの波動関数も崩壊して属性値bが確定したはずだ。だが粒子Bのどの時刻で崩壊は起こったのだろうか。
各観測者は、Aの崩壊と同時刻だとして、自分の座標系を基準にして判断したそのBの時刻を、属性値の観測結果と一緒に、粒子Bに対して静止しているもう一人の観測者S4に向けて電磁波信号を送って報告したとしよう。S4はその三者からの報告を時刻t4で受け取り、Bの属性値bを知る。誰からの報告も、その属性値に違いはないが、Bの波動関数が崩壊した時刻は各々が異なっている。いったい波動関数の崩壊はいつ起きたと考えればよいのだろうか。それとも、S4にとってはt4で属性値が判ったわけだから、崩壊の時刻はt4だと考えるべきか。だとすれば、逆にAの方の崩壊は、観測が実行されて暫く経ったあとだということになってしまう。観測されたのに波動関数の崩壊が起きていない時間が存在する。これはおかしい。
私は量子力学の理論内容そのものに楯突こうなどという気はもちろん毛頭ないが、波動関数の崩壊という観測問題上での解釈はどうも納得がいかない。
一方で前節で示したように、同時刻の相対性は完全決定された世界像(時空的決定論)をクローズアップさせている。私は、(直観的なものでしかないが、)この世界像と量子力学はひょっとして両立するのではないか、多重世界論とは別に、波動関数の崩壊という解釈を必要としない考え方が可能ではないかと思っている。その基本的着眼点は、量子力学の理論も概念も四次元時空内存在としての意識のあり方の一つだということ、とりわけ、確率という概念をその視点からどう捉えるかということである。
そのためには、量子力学的概念がどのように形成されてきたのかというところから根本的に検討して行かなくてはならないかもしれない。とりあえず、本稿では以上のような問題提起にとどめることにしよう。また稿をあらためてこの問題に取り組んでみたい。
indexへ
五 倫理学上の問題について
(1)折り合い 我々は通常、「過去は決まり、未来は決まっていない」という前提の上で生活しているように思える。そして、様々な法や取り決め、倫理規範のかなりの部分がそれに立脚している。だが、これまでの考察が正しいとすれば、独我論に徹しでもしない限り、この前提は否定されなくてはならない。すなわち、過去も未来もともに決まっているか、ともに決まっていないかのどちらかの世界観を採用するしかない。だとすると、人類の法や倫理規範すべてを見直して変更しなくてはならないのか。
これはおおごとである。私はどちらかといえば保守的なので、できれば事をあまり荒立てないでおきたい。そこで、相対論や量子論が近似法則として古典力学の有用性を守ったように、有用性のある価値基準として、「過去は決まり、未来は決まっていない」という世界観をそうでない立場から再定立できないだろうかと思った。それができればとりあえず安心だ。しかし、倫理的価値観というのはストレートに究極性を欲しがるから、物理学のような具合にはいかないかもしれない。が、とりあえず、一つの課題として挙げておこう。
(2)選択 「未来と同様、過去も決まっていない。」その立場を否定する完璧な根拠を私は知らない。多重世界論であれば、可能のような気もする。そして、場合によれば、こちらの方が気分的には心地好いかもしれない。ただ、少なくとも私の意識にとっては、過去は一通りのあり方で決まっているという厳然たる事実を重視したい。そこから目をそらすのは哲学の放棄ではないだろうか。だから、私は「未来も過去と同様、完全に決まっている」という立場を取る。これは証明ではない。選択なのだ。
(3)自己意識 私は時々こんなことを考える。もし、自己意識がその唯一性から解放されて、例えば時分割で様々な人の自己意識に順次乗り移っていくようなシステムになっていたら、人類の苦悩の大半はなくなっていたのではないかと。
しかし、自己意識というのはとてつもない唯一性を担わされて、諸悲喜劇の根源になっている。この自己意識というものと実によく似た概念、それが「今」という概念なのだ。
「今」とは何か、そして「私」とは何か。この問いこそが倫理学的考察の一番基底に来るべきではないだろうか。私はそんなふうに思っている。
人は往々にして「未来が完全に決まっている」という考え方を好きになれないのは何故だろう。しかし、時として、人は積極的にこのような考え方を取る場合がある。運命論は必ずしもペシミズムになるわけではない。むしろその逆であることが結構あるものだ。そのとき自己意識はどうなっているのだろうか。自己意識が宇宙と一体となっているくらい無我に達してはいないだろうか。
とりとめのないように思われるかもしれないが、「同時刻の相対性」への着目に始った私の関心はそんなところまでひろがっていきそうなのである。
indexへ
戻る